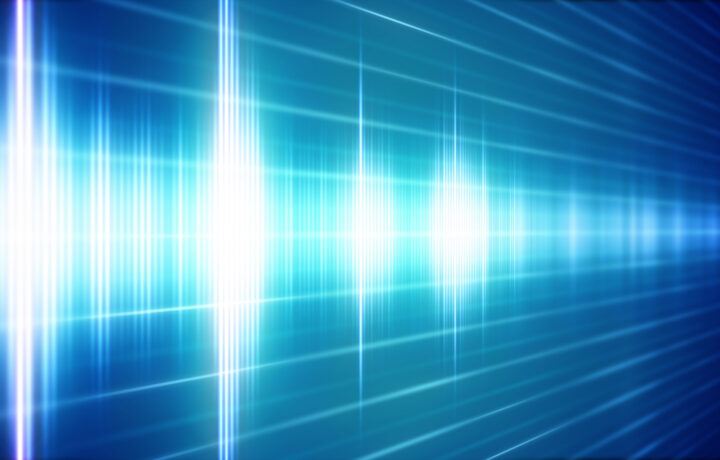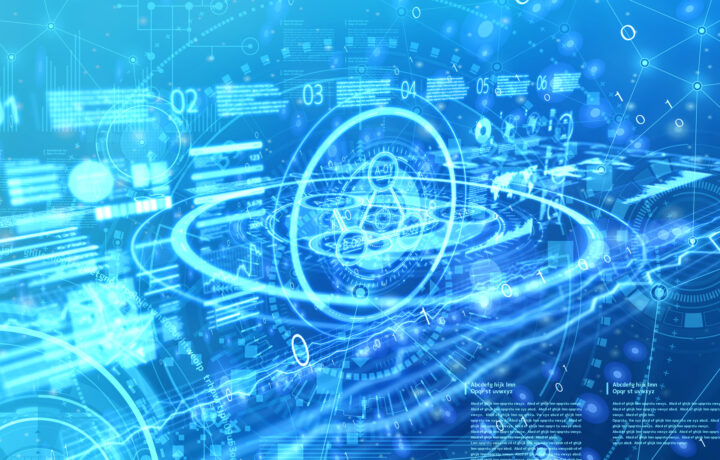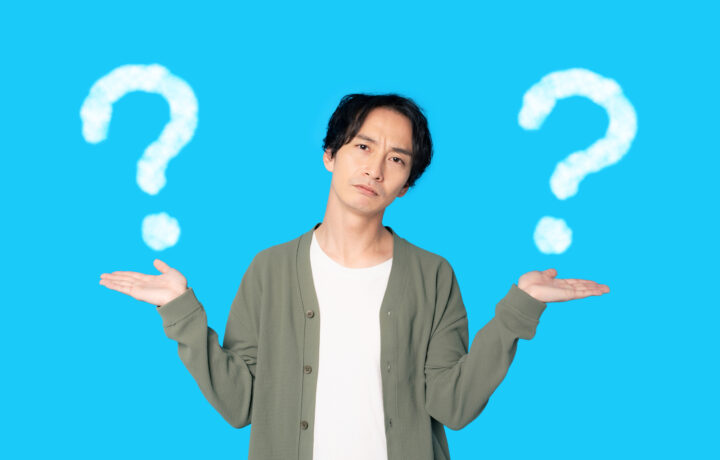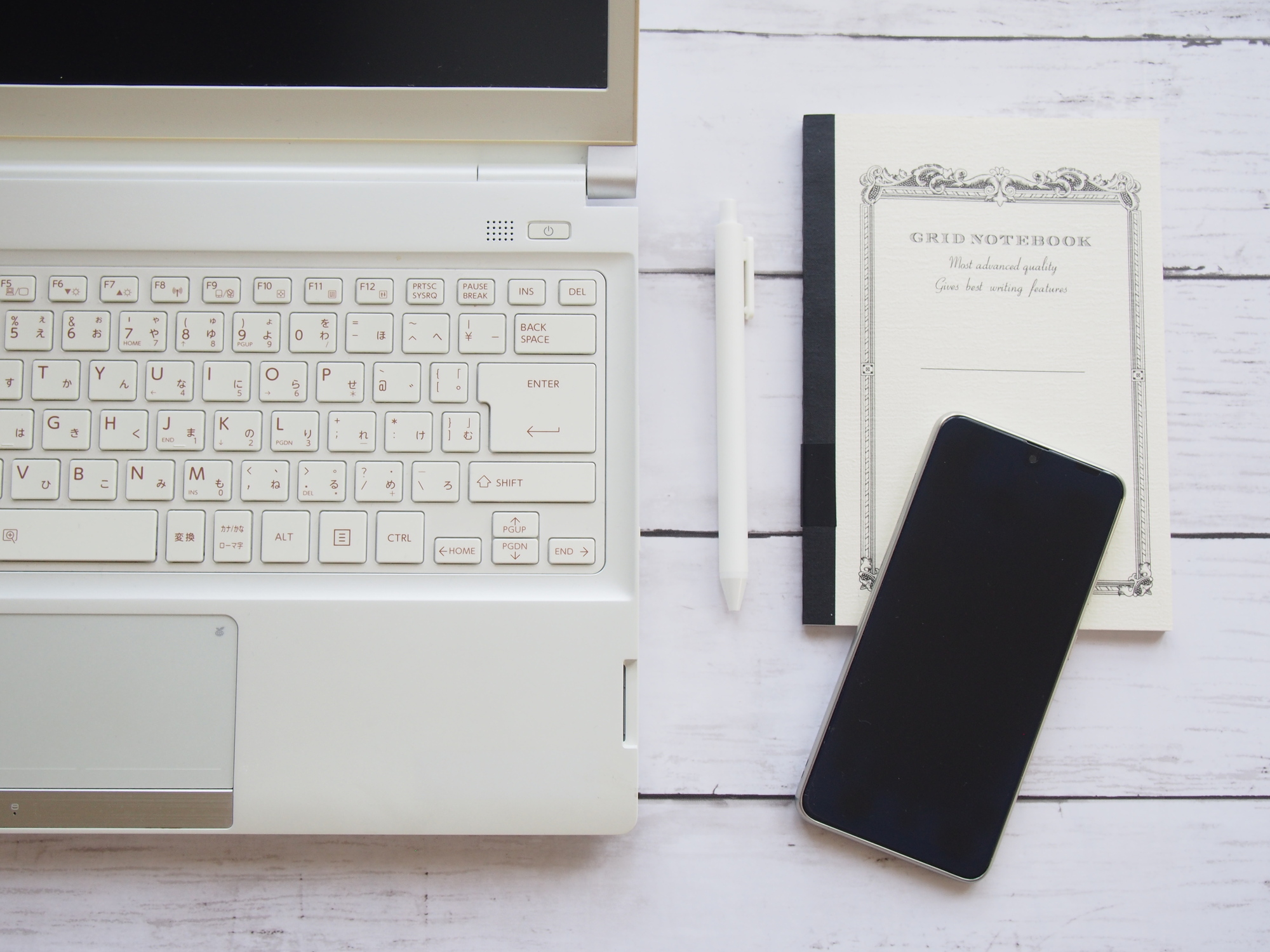Sound Craft Schoolで提供しているサービスの内容です。
このサービス以外でもお気軽にご相談下さい。
Sound Craft Schoolで提供しているサービスの内容です。
このサービス以外でもお気軽にご相談下さい。
近年では、AIによるミックス・マスタリングが主流となり、iZotope製品等でもおおむねMix/Masteringが出来るようになりましたが、私達からすると、ある程度ミックスアシスタントとして使うレベルであると感じています。
多くの方が、AIでやってみたけど、何が問題なのかわからない、YouTube等で紹介している方の動画を見ても、プラグインの説明ばかりで、それを購入すれば本当に出来るのか不安など、方向性を見失ってしまった方向けで、丁寧に何が問題であるか解説して理解をしてもらい、実際に自身で出来るようにスキルアップして頂きます。
このような場面に遭遇している方は、是非サービスを検討してみて下さい。
オンラインでワンツーマンで「聞きたいこと」を遠慮なく相談して下さい。
音に関すること、例えばエフェクターの音、アンプの音、実際のCDの音、レコーディングでの音、その他色々な音に関して、どのようになっているのか、またその音がどのような考えで存在するのか、楽曲に取り入れる音の選択も困っているなど、「音」に関する全ての質問をぶつけてみて下さい。
AIでも質問はして回答をしてくれますが、実際にその内容を理解するまで、音を知らないと到底難しいので、オンラインレッスンで、データなどもみながら習得できる環境を整えましょう。
全ての「音」は、周波数というものを持っています。
この周波数を「聴く」のではなく、「見る」ことで、音に関する世界感は大きく変わります。例えばバンドアンサンブルで音が抜けないから「大音量」にしてしまうギタリストは多く見受けられるし、ボーカルの帯域をガンガン責めているベースの方も多く見かけます。私自身、大昔はその傾向にあり、周波数の「極意」を知るまで長い時間を要しました。
この周波数を「見る」ことで、あなたのサウンドはずば抜けて「聞こえやすく」「聴きやすく」「邪魔しない」音に生まれ変わるでしょう。
この音をどう作っているのかなども、1部、周波数が影響しているものもあるので、是非、この周波数を極めてみて下さい。
DAWでミックス、マスタリングをしている方、1度は、このタイトル通り、「プラグインのドロ沼」に嵌まることがあるでしょう。多くの方は、「正しくプラグインの存在を理解していない」ことが多く、例えばWavesのRBassがなぜ存在するのか、どういう場面で使うのかという考えを「正しく」持たないことが原因です。
コンプレッサーにも多くの種類があり、有名なところでは、LA-2A、FairChildなど、有名なものから、デジタルのものである、WavesのC1、FabFilterのPro-Cなど、これを使い分けることがなぜ必要なのかもわからないまま、YouTube動画をみて、「やってみる」をしてしまっています。
そうすると、多くのYouTuberさんは、「これがいい」「あれがいい」と言うでしょう。この購買意欲を注ぐ言葉が、「プラグインのドロ沼」に向かうのです。
私達は、このプラグインを、何故、どのように、結果をどう得るか、これがどのような影響を及ぼすか、使わなくても良い場面はないか、など、様々な考えでプラグインを使用します。
こういう沼に嵌まってしまった方は、是非、受講をしてみて下さい。
※DAWソフトウェアは、受講者様に操作してもらい、私は1つのDAWで操作します。この方が、お互いに覚えなければならないことは「少なく」、「元の問題」に集中出来るからです。
みなさん、例えばレコーディングをしているシーンを想い浮かべて下さい。
ボーカルでは、目の前にボーカルマイクとポップガード、収録卓、こんなイメージでレコーディングをしている映像を見かけると思います。エレキギターもレコーディングの際は、オンマイクでレコーディングするケースもありますし、ベース、ドラムなども同じくマイクにて収録します。
ここで、音の原理を知らないと、大変な「落とし穴」に落ちてしまいます。
バンド活動をしている方は、1度は経験があると思いますが、「あれ?今日の音は抜けないな」「聞こえ方が違うな」というシーンです。そうすると、ギターでは、アンプを調整したり、エフェクターを調整して、また次の時に違うように聞こえるパターンです。
これは「音が変わる原因」を知らないから、このように対応をしてしまうのです。
私自身、バンドアンサンブルで演奏している際、このパターンは毎回のように遭遇しますが、原則、マイクを使っているものでも、ラインで流しているものでも、「音が変わる」ことは理解しないとならないです。
このような「なぜ音が変わる?」という根本を学びましょう。
私もバンドマン時代、ある方のサウンドを真似しようと頑張って研究をしたものです。懐かしい話しではあります。
よく、YouTubeでも○○さんのサウンドを再現!、こうやって○○さんのサウンドは作っている!という過大なことをいう方はいます。あながち、間違えではありませんし、趣味ではこれで良いでしょう。
しかし、プロとアマチュアの違いをしっかり理解している方は、「絶対に真似が出来ない」とわかっています。
近づけることは出来ても、ドンズバ機器を買っても、絶対に真似が出来ないのです。音を知っている方は、これは「常識」に当てはまるものであり、お金、機材、ギター、ベースなどの弦楽器等の問題ではないのです。
そして、自身の「音」をどういう風に作るのか、これも迷っている方は大半です。これも「真似出来ない」音を作ることが「自身の音」に繋がると思いませんか?
こういう「音を理解する」「真似出来ない音を作る」「最終的に自分の色にする」というフェーズをしっかり学び、実践をしてみましょう。
各コースはコマ数で管理されております。
そのコマを「どの教育」に使うのかは自由になっており、パック(例、ミキシング/マスタリングコース)が10コマである場合、その5コマを別のパック(エフェクター講座等)に割り振る、もしくは、10コマで契約した上で、フリーで質問、解決をするなど、組み合わせは様々です。
こちらでは、コマ数で管理をしておりますので、他社にはない、フリーな形でのカスタムプランもご利用頂けます。
是非、色々な「音」に関する質問、疑問、解決をトライしてみて下さい。
コマ数の消化については、「ご自身の空いた時間」と「こちらのスケジュール」が合致することで、レッスンを受けることが出来ます。
必ずしも、ご希望のお時間に受けられるとは限りませんが、講師のスケジュールにより、出来るだけ合わせた形でレッスンを行う仕組みになっておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
また、1コマのレッスン時間と、連続して2コマ使いたいというレッスンもお受けしております。
早く知りたい、習得したい方は、連続で2コマを使う、3コマを使うなど、シーンによってフレキシブルに対応出来ますのでお気軽にご相談下さい。
まるで、隣にいて教育するようなイメージでワンツーマンレッスンを行えます。
このレッスン方式は、インターネット回線を使ったものとなりますので、最低でも光通信環境が必要となります。
もし光回線ではないもの(VDSL、ADSL等)である場合は、テキストレッスンもお受けいたします。テキストレッスンとは、当方にてレッスン材料をテキストベースの資料で配付し、その内容を読み上げながら指導をするスタイルであり、画面共有をしない形となりますので、音声のみインターネットに流れるので低負荷です。
光回線の場合は、ZOOMで受講となります。ZOOMの場合はこちらよりアクセス可能な時間とURLを配付いたしますので、それをクリックすることでお互いの環境にて相互通信が可能になり、レッスン内容は収録されますので、後日見直すことも出来ます。
また、画面共有機能により、こちらのパソコンや、お客様のパソコンを共有した上で、レッスンを進めることも可能可能です。これにより今までお一人でやっていた内容を講師が見ながらアドバイスや指導をすることも出来ます。
また、エフェクター等の講座である場合、基本的には音声データは取得してもらうか、DAWにLitentoというツールを入れて頂き、DAWを経由してこちらが聞こえるように設定しますのでご安心下さい。
※場合により現地出張も可能ですが、別途料金がかかりますのでご相談の上、御見積いたします。
「音」という存在を知ることで、ご自身が「聴いていた音」から「何でも作れる」に生まれ変わります。これは、音の存在がどういうものであるか、そして音がどういう形で表現されているのかを知ることに繋がります。
1例ですが、レッスン内容に「音痩せ」というものが何であるのか、という課題があります。多くのギタリストは、エフェクターを接続したら音痩せが酷い、あの人のサウンドは音痩せしているという話しをします。
しかし、それは音痩せなのでしょうか。ここに真意がないまま、固定概念で「音痩せ」という言葉が先行し、凝り固まった考えになり、その考えを他人に伝えている、悪循環が良く見えています。
我々は、音痩せが何で存在するのか、防止出来るものなのか、それを感じさせないためにどうするのか、色々なテクニックや考えを持って、その「存在」に対して対応します。
また、音に対してはノイズ(サーノイズともいいます)も1つの音ですが、嫌う人もいれば、これがないと駄目だという人もいます。音の存在は、このように複雑な要素で決まっています。
これらを「知る」ことで、論理的な説明ができ、その対策を論理的、物理的に出来るということがゴールです。
Copyright © 2025 Sound Craft School. Allright reserved.